自社に学習管理システムを導入するなら、LMSとeラーニングの違いについて理解しておく必要があります。
そこでこの記事では、以下の内容を解説します。
- eラーニングとLMSの違い
- eラーニングの課題とLMSで解決できること
- LMSの導入形態
- 導入前にしておくべきこと
自社教育を効率的かつ効果的に行うためにも、LMSについて正しく理解しましょう。
eラーニングとLMSの違いとは?
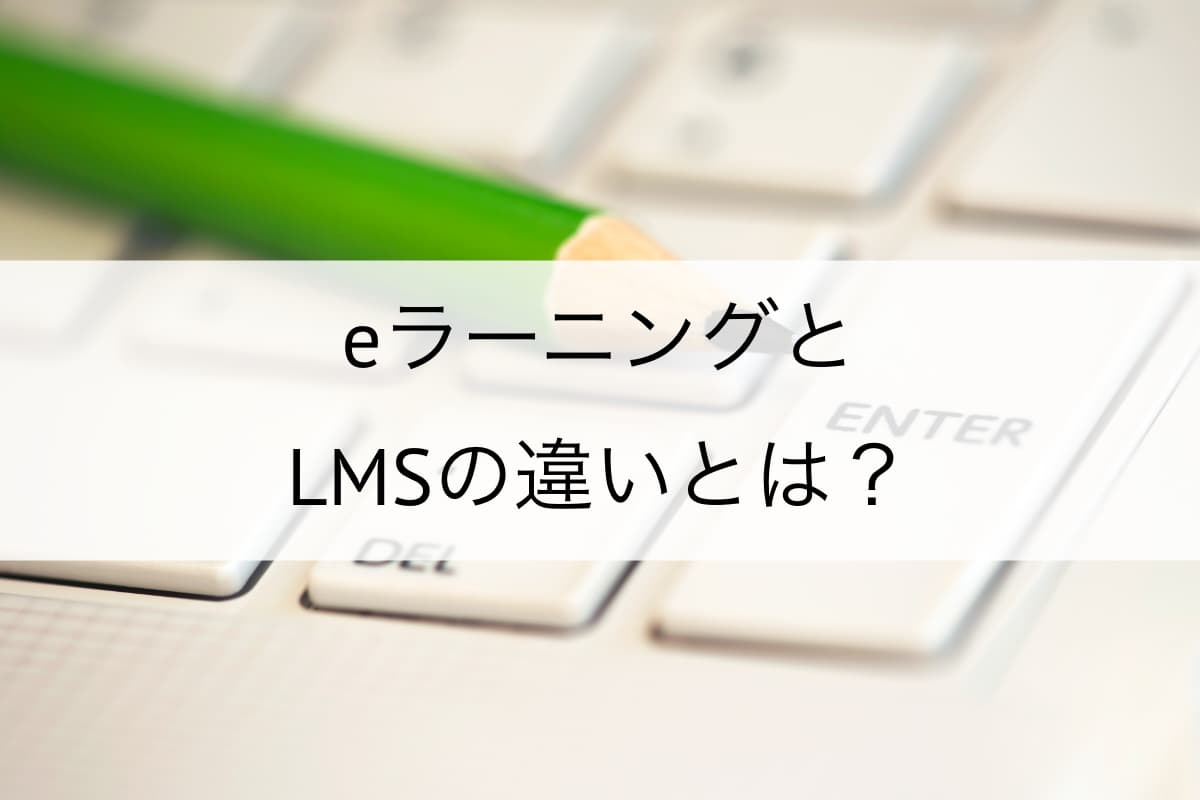
この章では、eラーニングとLMSの違いが理解できるように、それぞれの言葉の意味について詳しく解説します。
eラーニングを理解する上で重要な知識となるので、ぜひご覧ください。
eラーニングとは?
eラーニングとは「electronic learning」の略であり、WBT(Web Based Training)の意味でも用いられます。インターネットを経由したオンライン学習ツールであり、近年人材育成や組織の課題解決ツールとして注目を浴びています。
インターネット環境下なら受講場所・時間に縛られることなく、仕事の合間や出先のスキマ時間を有効活用して学習することが可能です。
ほとんどのeラーニング教材では、動画配信機能やテキスト、テスト機能が備わっています。受講者の学習ニーズに合わせた教材に対応しているため、モチベーション維持・向上が期待できます。
LMSとは?
LMSとは「Learning Management System」の略称で、eラーニング学習を効率化するための管理システムです。
例えば、LMSには以下の機能があります。
- 学習管理機能
- 教材管理機能
学習管理機能には、受講者の進捗状況確認や個別カリキュラムの作成、学習促進のためのメッセージ配信機能等があります。受講者がeラーニング学習を効果的かつ効率的に行うことができるサポート機能が備わっています。
一方、教材管理機能では、既製品教材の購入や自社独自の教材作成ができます。サービス提供会社によっては教材作成サポートもあるため、自社にあった形式で教材を導入することができます。
eラーニングシステムとLMSに違いはある?
LMSと同義の言葉に「eラーニングシステム」がありますが、いずれも意味に大きな違いはなく、どちらもeラーニング学習を効果的に行うために管理するシステムを示す言葉になります。
eラーニングには課題点があった
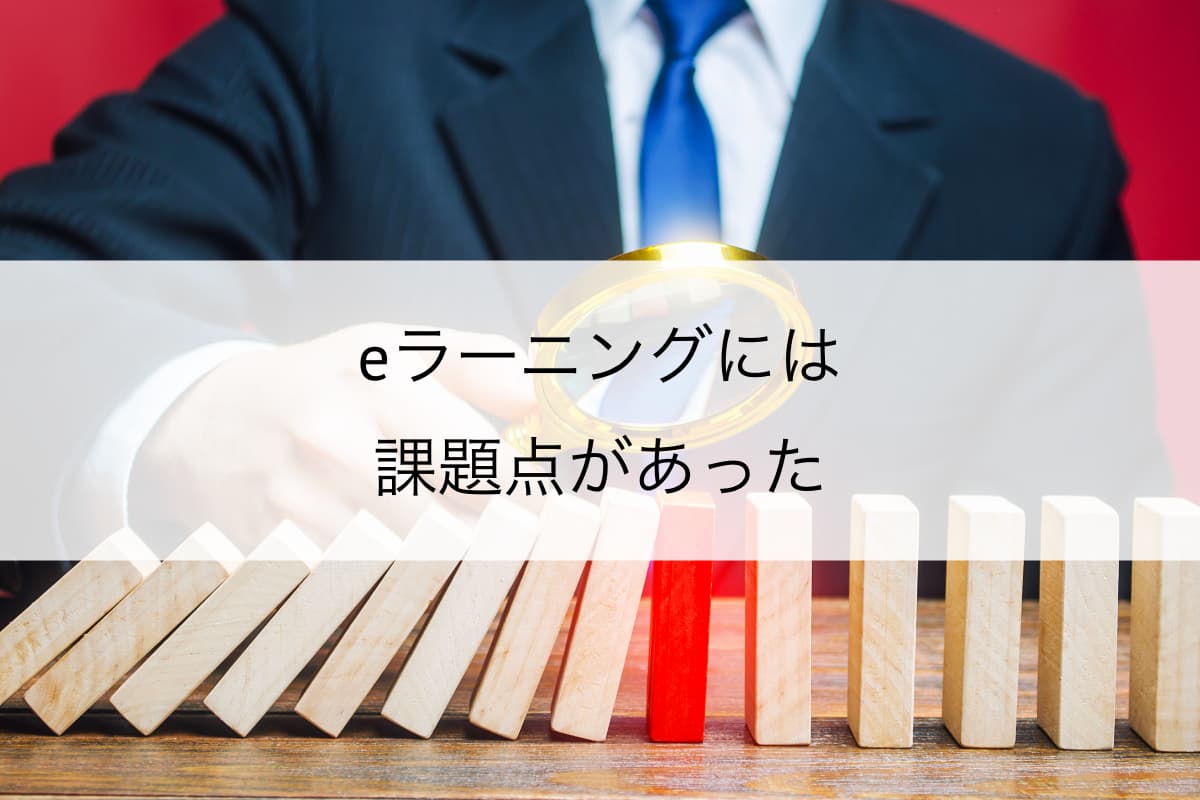
これまでのeラーニングには以下のような課題点がありました。
- 組織的な学習にならない
- 受講状況の確認が難しい
組織的学習にならない
従来のeラーニングは教材ファイルにアクセスしてテキストを見て学ぶスタイルがメインの、配布型学習であり、以下のような課題がありました。
- 受講者のモチベーション維持が難しい
- コミュニケーションが取りづらい
配布型教材は受動的な学習であるため、受講者のモチベーション維持が難しいことが課題でした。またコミュニケーション機能も備わっているわけではないため、リアルタイムに疑問を解決できず、相談相手が作れないという課題がありました。
社員は個々に業務の合間に自主学習に取り組まなければならず、孤独な戦いとなりがちでした。
このように配布型教材で行う学習には様々な課題がありました。
受講状況の確認が難しい
従来のeラーニングでは受講状況の確認が難しいという課題もありました。
具体的には、以下の2つです。
- 進捗状況や学習レベルの把握ができない
- 学習ニーズを把握するシステムがない
受講者の進捗状況や学習レベルを把握できないため、導入後の効果を実感しにくいという課題がありました。また、受講者からのフィードバックを得られるシステムがないため、教材自体の問題点抽出や改善策検討が難しく、学習ツールとしてまだまだ課題がある状態でした。
LMSはeラーニングの課題を解決できる

本章では、eラーニングがこれまでに抱えていた課題を、LMS導入によって解決できることを、以下の4つの視点から解説します。
- 教材の管理
- 学習状況の管理
- 受講環境
- コミュニケーション機能
上記の機能は導入するLMSによっては搭載されていない場合がありますので注意しましょう。導入前にサービス内容をしっかりと確認しておくことをおすすめします。
おすすめのLMSについてはこちらで比較しておりますので合わせてご覧ください。
【2022年最新】おすすめLMS(学習管理システム)比較10選を紹介
教材の管理
LMSには教材の管理機能があります。
教材の種類は、テキストやPDF、動画やWebセミナーの配信などがあり、様々な形式で教材を配布することが可能です。
サービス提供会社によっては、教材作成サポートを行っている場合もあります。既存の教材だけで学習ニーズを満たせない場合、自社オリジナルの教材を作成することで、より効果的に学習を促すことができるでしょう。
CDやDVDとは異なり、一度作成して公開した教材であっても、新しい情報を追加したり古い情報を更新したりできるため、常に受講者に最適な教材を提供することができます。
学習状況の管理
LMSには、学習状況の管理機能もあります。
学習履歴や進捗状況をリアルタイムに把握したり、テストの点数を集計・分析したりもできるため、受講者の学習意欲や到達度を簡単に把握できるようになりました。 また、このような機能を応用することで、人事評価の指標として活用することもできます。
その他、アンケート機能を用いて進捗状況やテストの点数では測れない課題や悩みを受講者から抽出し、学習管理の改善や個々に適した学習コンテンツの作成も可能です。
このように教材だけでなく、受講者ごとの状況を考慮した学習管理ができるのもLMSの魅力と言えます。
受講環境
自由に受講環境を選べるようになった点もLMSの魅力です。
インターネット接続のできるパソコンやスマートフォンなどの端末があれば、場所や時間に縛られることなく受講することができます。ただし、すべてのLMSが各種モバイル端末に対応しているわけではないため、注意が必要です。
コミュニケーション機能
コミュニケーション機能により、受講者のモチベーションや理解度を把握しやすくなりました。
コミュニケーションに関する具体的な機能は、以下の通りです。
- アンケート機能
- チャット機能
- ライブ配信機能
これら機能により、相互にコミュニケーションを取りながら学習を進められるようになりました。
例えば、アンケート機能を利用することで受講者のニーズの深堀や課題の抽出・改善を行うことができます。チャットやライブ配信機能ではリアルタイムで質問やフィードバックを行うことができ、受講者の理解を促すことに繋がります。
LMSの導入により、これまでの一方向的な学習から、相互にコミュニケーションを取りながら進める学習が実現したと言えます。
LMSの導入形態

LMSの導入形態には、以下の2つがあります。
- オンプレミス型
- クラウド型
各特徴を理解し、自社に最適な導入形態を選べるようになりましょう。
関連記事:【LMS】クラウド型とオンプレミス型のメリット・デメリットを比較
オンプレミス型
オンプレミス型とは、自社サーバーに LMSをインストールもしくは構築する導入形態です。
サーバーやインターネット環境などのインフラ整備に加えて、システムの構築に時間がかかります。一方、操作性や機能などを柔軟にカスタマイズでき、自社に最適化された学習システムを構築できるというメリットがあります。
システムを構築するための初期費用が高く、管理・メンテナンスの人員が必要になりますが、ランニングコストを抑えつつ、自社に適したLMSを使用することができるため、長期的に運用を見据えている場合におすすめの導入形態です。
クラウド型
クラウド型とは、サービス提供会社がすでに構築したLMSをインターネット経由で利用する導入形態です。
システムの構築が不要であるため、初期費用を抑えることができます。また管理・メンテナンスはサービス提供会社が一括で行うため、システムの運用に人員を割くことができない企業でも導入しやすいというメリットがあります。
クラウド型の料金体系は、主に月額固定制と従量課金制の2種類があります。利用者数(ID数)が多い場合は月額固定制、利用者数が限られている場合は従量課金制等、状況に応じて適した料金体系を選択することが重要になります。
LMSの料金についてはこちらの記事でも解説しておりますので、合わせてご覧ください。
LMS(学習管理システム)の費用相場とは?種類別料金・ポイントを徹底解説
LMSの導入前にしておくべき4つのこと
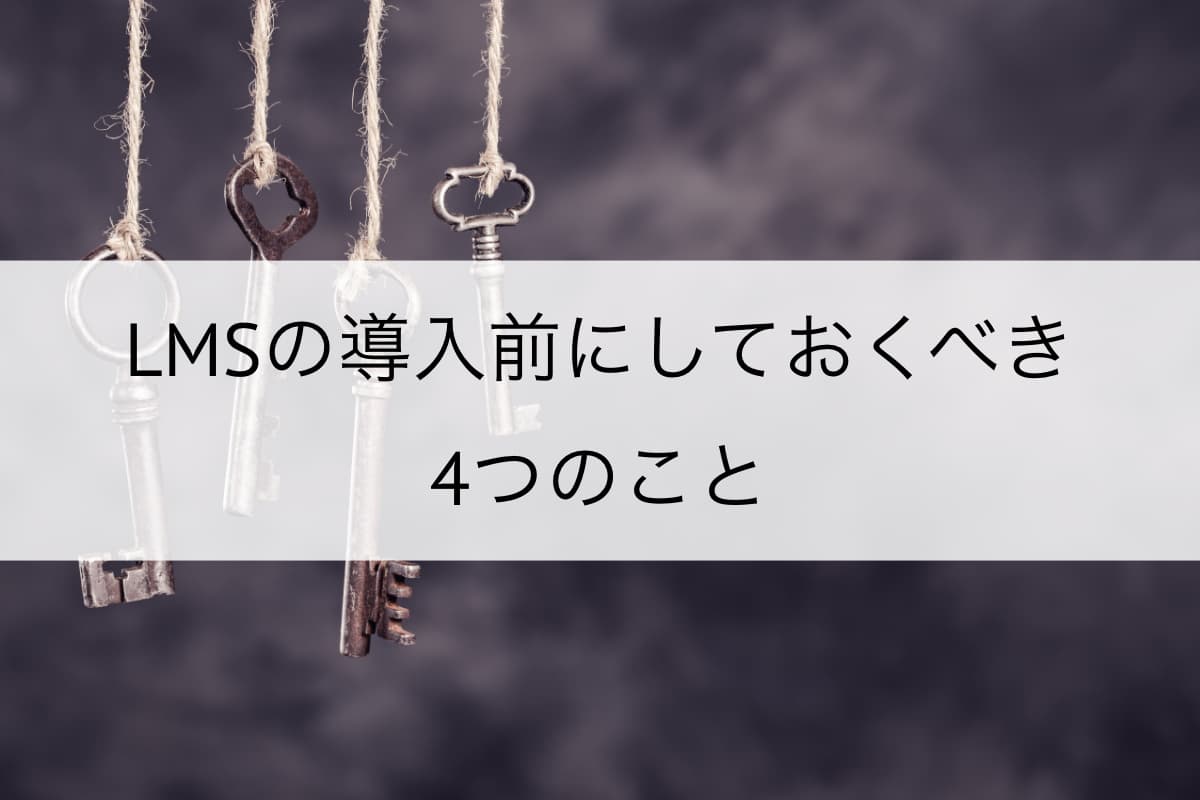
LMSの導入前にしておくべきことは、以下の4つです。
- 導入目的を明確にする
- 教材を確認する
- 導入環境を確認する
- 運用・管理のルールを作る
この4つを事前に準備しておくと、スムーズなLMSの導入に繋がります。
導入目的を明確にする
まずLMSの導入目的を明確にしましょう。
導入目的を明確にすることで、自社に必要な教材や機能などを選択する基準を持つことができます。目的を明確にしないままLMSを導入してしまうと期待していた効果を得ることができない場合があるため注意しましょう。
例えば、常に最新情報を受講者に与えるという目的でLMSを導入する場合、教材コンテンツの修正が容易であったり、様々なデバイスで受講できたりするなど、操作性がシンプルであることがLMSを導入する際の重要な判断基準になります。
このように導入目的を明確にすることで、どんなLMSが自社にとって最適かを比較・検討できるようになります。
教材を確認する
LMSを導入する前に教材の確認をしましょう。
確認事項は、以下の通りです。
- 既製品教材の内容
- 教材の質・量
- 教材作成サービスの有無
当然ですが、LMSのサービス提供会社によって用意されている教材が異なります。そのため、どのような内容の教材が既製品として準備されているかを確認しておく必要があります。新入社員に向けたマナー研修教材が充実しているLMSなど、目的に沿った教材があるかどうか、必ず確認をしておきましょう。
また、教材の質や量を確認しておくことも大切です。教材の質や量に不足があった場合、導入後に教材の補充や作成が必要になり、手間が増えてしまいます。
独自教材の作成を希望する場合でも、導入するLMSに作成サービスがあるかどうか確認しておきましょう。教材の作成が容易にできるかどうかも確認しておきたいポイントです。
環境を確認する
LMSを利用する環境の確認も大切になります。
例えば、受講側の環境では以下が挙げられます。
- パソコン
- スマートフォン
- タブレット
導入予定のLMSが上記のような端末で利用できるかどうかによって受講者の学習頻度やモチベーションが変わります。管理側・受講側の視点から利用環境を想定し、最適なLMSを選びましょう。
運用・管理のルールを作る
LMSは導入して終わりではありません。導入後は管理やメンテナンスが必要になります。
管理・メンテナンスを担う部門の設立や責任者をあらかじめ考えておくと、導入後にスムーズに運用することができます。
また、管理・メンテナンスに不安がある場合は、サポート体制が充実しているLMSがおすすめです。サービス提供会社により異なりますが、困ったことが起きた際にすぐにチャットや電話で相談できる環境であれば安心です。
サポートのアクセス方法や活用方法については導入前に確認しておきましょう。
eラーニングとLMSの違いを理解しておこう
以上、eラーニングとLMSの違いについて詳しく解説しました。
要点を以下にまとめます。
- eラーニングとはオンライン学習で、これらを管理するためのシステムがLMS
- LMSとeラーニングシステムは同義語
- LMS導入でこれまでのeラーニングの課題を解決し、効果的な学習を実現できる
- LMSの導入形態は「オンプレミス型」と「クラウド型」がある
- 目的や教材・環境について導入前に確認しておくことが重要
LMSを導入することで学習や教材の管理を効果的・効率的に行うことができます。
一方で、LMSの効果を最大限発揮するためには、導入前にLMSに対する理解を深め、導入目的を明確にしておくことが重要になります。
eラーニングシステムを導入するなら「LMS365」
eラーニングシステムを導入するなら「LMS365」がおすすめです。
導入するメリットは、以下の3つです。
- 導入が簡単
- 簡単にコンテンツを作成・配信・管理できる
- Microsoft365上で稼働する唯一のLMS
LMSの導入する企業にとって最も不安なのが、システムの構築と運用管理ではないでしょうか?
LMS365なら新たにサーバーを用意する必要はなく、既存システム(Microsoft365)にインストールをするだけなので簡単に導入できて、セキュリティ面も安心できます。
Word、Excelをはじめ、様々なファイル形式に対応しているため、従来から慣れ親しんだツールでコンテンツの作成や配信、管理ができます。そのため、導入後に操作がわかないという利用者や管理者のストレスは軽減されます。
LMS365なら導入前後のストレスを感じず、簡単に学習システムを構築できますので、この機会にぜひご利用ください。デモサイトでの体験もできますのでお気軽にお問い合わせください。
簡単に学習教材として利用できるLMS365がおすすめです。
まずはお気軽にお悩みや課題をご相談ください!
